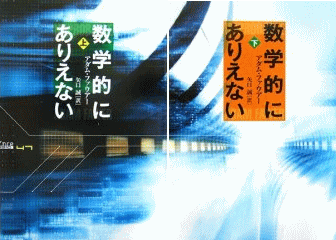
数学的にありえない アダム・ ファウアー著
文藝春秋 2006年8月刊
一言で言えばこの本は、ダビンチ・コードの物理版である。
ダビンチ・コードが美術史的事実を絡めながら通説とは違う解釈と論証を交えながら一つの連続殺人事件を解き明かすという画期的サスペンスだったように、この本は美術史的事実を物理学上の理論と事実に置き換えて、末来予知が出来る人間及びそのメカニズム解明を巡り、情報機関が暗躍する超人的スパイアクションと言える。
原作の作りは、ダヴィンチ・コードに比べたらはるかに映画向きである。
末来予知能力のある主人公が場面場面で伏線となる行動と発言をしまくるからである。
読者及び観客にはそのことの辻褄が後になって腑に落ちるという趣向である。
昨今のサスペンスではこういう通説的事実に対する有力説に基づく反証をベースにする、みたいなものが流行りなんだそうだ。しかし、これはこと量子物理学の知識をどこまで理解できるか、知っているかにかかってくるため、ダビンチ・コード的万人向きのわかりやすい話とはなってない。
しかし、高校で物理も地学も3というパープリンな人間にとっては計算することなく、単に理論の話として読めて再度物理学の常識的な概要を勉強しなおすよい機会とはなった。
「3」(といっても、10段階評価じゃないかんね!)の人間がこの頭にも顧みず語弊・曲解を恐れず解説するに、みんなが狙って暗躍する、この主人公の一見荒唐無稽と思われがちな「末来予知能力」の根拠は次の様な物理学の理論によるらしい。
17世紀、アイザック・ニュートンに代表される決定論の古典物理学者は、「この世界のあらゆる事象や出来事は、全て物理法則によって決定されており、不確定なものなど何もない。これから起こるすべての現象は、これまでに起きたことに起因する」と考えており、「究極の統一理論が解明され、ある時刻における宇宙のあらゆる情報が与えられれば、末来は完璧に予言できる」と信じていた。即ち、人間の目にでたらめにしか見えないのは単に人間がそれを計測する能力が無いからに過ぎない、と云う事である。そしてこの古典物理学のもっとも重要な教義は、ニュートンが「プリンキピア」に現した「物体の運動はそこに働く力の大きさによって決まる」という『運動の法則』だった。
従ってこの理論からは当然もしも全ての物理的データを元に能力さえあれば末来予測が可能という結論になる。それを信じてその予言することに挑戦し続けた学者達がいた。
その中の一人が、シモン・ピエール・ラピラスである。ラピラスは確率論を用いることで予測の誤差を最小化し、それにより間違っている可能性のもっとも低いもの予想として提示する方法を試みた。
すなわち、この宇宙が決定論的なものだと信じたラプラスは、『物理の法則を理解し、宇宙に存在する物質粒子のある瞬間における位置をすべて知っている人間がいれば、その人間にはこれまでに起ったことすべてのことが解かるだけでなく、末来の歴史も完璧に予言できるだろう』と考えたのである。
これが、この著作の目玉『ラプラスの魔』である。
しかし、この決定論ははやくはダーウィンの『種の起源』における突然変異の反証及び20世紀のハイゼンベルクという物理学者の『物質粒子は観察されない限り特定の位置を持たない』ことの証明によって否定された。つまり、この事は、ニュートンが「すべてのものは時空においてある特定の位置を持っている』と考えたことを否定するものである。
このハイゼルベルクの不確定性理論は、1926年に発表されたもので、「現実世界において、物質粒子ははっきりとした位置をもっていない。単に確率的な位置をもっているだけだ。」というものであった。平たく言えば、それぞれの粒子はどこかある場所には存在しているが、観察されるまではある特定の位置をもっているわけではないということだ。
ハイゼルベルクはこのことを以下の様にして証明した。即ち、
電子や陽子といった目に見えない物質粒子の位置を観測するには、粒子に電磁波を当てる必要がある。このときの電磁波の崩壊パターンを分析することで、粒子の位置を知ることができる。しかし、この実験は好ましくない結果を引き起こしてしまう。電磁波と衝突した時に粒子が跳ね飛ばされてしまうため、正確な運動量が観測できなくなってしまうのだ。
ここから導きだされるのは、物資粒子の位置と運動量を同時に観測することは不可能であり、物質界には常に一定の不確定性が存在しているという結論である。
ハイゼルベルクはニュートン派の科学者が常に支持していた絶対的真理を否定し、物質界とは灰色な曖昧なものであり、白と黒にはっきり分ける事はできないと主張。「現実世界において、物質粒子ははっきりとした位置をもっていない。単に確率的な位置をもっているだけだ。」と主張した。
さらにのちにコペンハーゲン解釈と呼ばれることになる量子力学を建設したニールス・ボーアを中心とする物理学者たちが「観察された現象は、観察されない現象とは違う物理の法則にしたがっている」と主張した。
この解釈が正しいとするとならば、いかなる物理現象も決定論的ではなく、確率論的であることになる。
更に極めつけは、20世紀初頭のかの有名なアインシュタインの特殊相対性理論が、時間と空間は相対的なものだとし、ニュートンが物体の運動において絶対的な存在だと考えた位置、速度、加速がじつはなにか別のものとの関係のなかで存在しているに過ぎないと主張するに至ったことである。なかでもとくに時間さえもが相対的なものだとする点が特に重要となる。
これにより物理学者達はどんなものも完璧な位置をもっていないばかりか、完璧な年齢ももっていないことを知らされることとなる。
この様にして決定論が否定されたならば、末来予測はもはや不可能なのか? 末来予測能力は存在しないのか?
この特殊相対性理論をベースに尚未来予測能力を論証するのがこの著作の一つの魅力ではある。が実証できない点で弱さが残る。
アインシュタインは更にその後、エネルギーと質量は本質的に結びついていることも証明した。そしてこの特殊相対性理論を通じて発見されたのが、すべての物質の基本成分たる素粒子―クォークである。このうち現実世界の物質はアップとダウンという二つのクォーク、それにレプトンというクォークに似た素粒子だけから成り立っており、このクォークとレプトンは実際には物質ではなくエネルギーだという点が重要となる。
つまり、量子物理学では物質は現実には存在していないことになり、古典物理学者が物質と考えていたものはエネルギーだということになる。
では、かくなる相対的存在たるエネルギーをいかにして予測することができるのか?
筆者はここでは、目には目をでは無いが、エネルギーにはエネルギーを、と云う事でエネルギーとしての思考のうちの集合的無意識こそが、相対化された時間たる末来にもアクセスして末来予測を可能にするものとの考え方を提示する。
この集合的無意識とはユングのいう無意識の3カテゴリーのうちの(一つは、任意に引き出せる個人的記憶、2番目は任意には引き出せない個人的記憶―いまでは思い出せない記憶とか、記憶の底に封印したトラウマ、そして)人の意識に上ることが絶対にない、起源のわからない知識のことである。生物学者が所謂DNAにプログラムされたものと信じているものがそれである。本能である。しかし、「獲得形質は遺伝しない」という生物学者には周知の事実が、人が生まれながらにして持っている本能の起源をDNAに求める事は自己撞着である。
物理学者はそれ――生物の遺伝的知識(本能的知識―だれからも教えられることなくもって生まれてきているもの)は意識に起源を持つと考える。
そこからエネルギーとしての集合的無意識を使って、時間も場所も相対化されたエネルギーとしての物質につながることにより末来予測をする。従って、ふだんは意識にのぼりさえもしないこの集団的無意識に体の何らかの器官を通じて接触できれば末来予測も可能となり、この接触できる器官を持つあるいはその能力のある主人公が未来予測が可能な貴重な存在となるのである。
しかし、このことは単なる仮説ないし理論であって、おそらく証明不可能なものなのだろう。だから、この本の原題がIMPROBABLE なのかな?
以上、かくのごとくに小難しい物理学理論をちりばめながら、筆者お得意の確率論も織り交ぜつつ話を進めるのだが、ダビンチ・コードではもう一つの単語の並べ替えという暗号解読の面白さが有った為に尚いっそう話が盛り上がったが、ここではそれに匹敵する謎解きが無い為、物理学理論を外せばともすると単調なスパイアクションの話でミステリーとしての面白さはあまり無いかもしれない。
やはり、この本で面白いのはあまり万人が目にすることのない物理学の論争の方だろう。確率論の話は、中学・高校での計算本位の確率論よりはずっと実用的で楽しめるかも知れない。
ノンストップジェットコースターサスペンスという触れ込みはやはりオーバーだといわざるを得ない。物理学で味付けしすぎた只のアクション小説だ。
戻る TOP